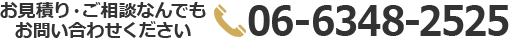- 大阪で金・貴金属買取ならゴールドウィン 梅田店・難波店ホーム
- 買取コラム
- 小判はいくらで売れる?価値ランキング10選や高く売るコツも紹介
小判はいくらで売れる?価値ランキング10選や高く売るコツも紹介
2025年3月21日
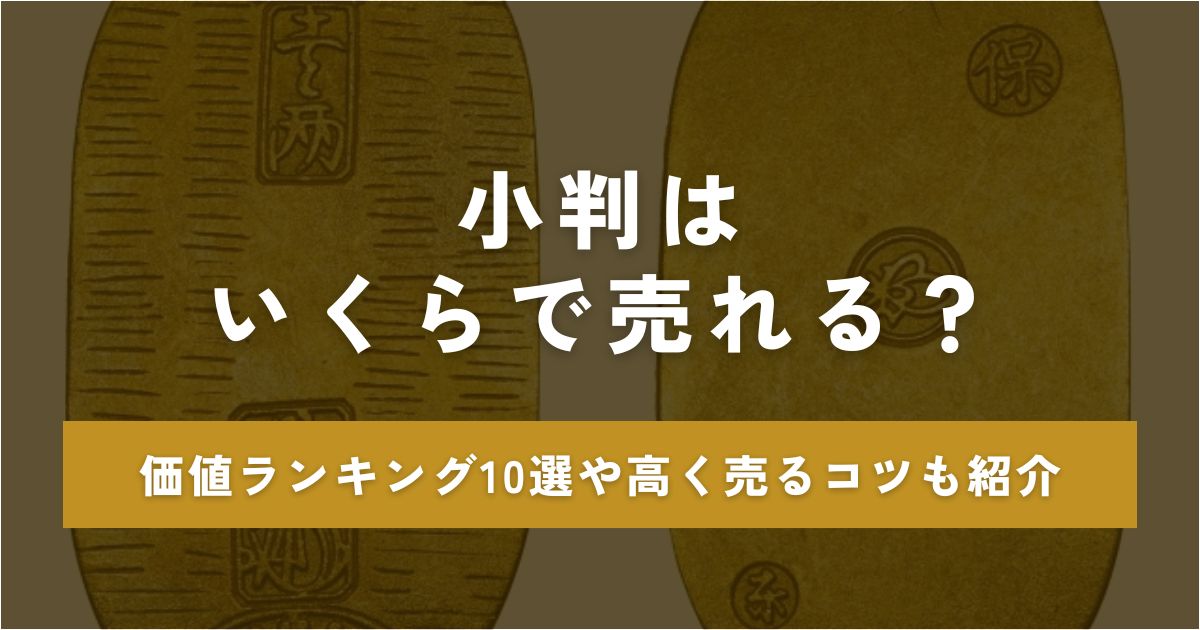
「小判の買取価格はどれくらい?」「小判を高く売りたい」と考えていませんか。
小判の買取価格は、種類や金の含有率、状態によって大きく変わります。価値を知らずに査定に出してしまうと、相場よりも安い金額で買い取られてしまう可能性があります。
後悔しないためにも、事前に価値や歴史的背景、高く売るためのポイントを押さえておきましょう。
この記事では、江戸時代の小判の価値ランキング10選を紹介しています。買取価格が決まる基準や高額査定のコツも紹介しているため、ぜひ小判がいくらで売れるか気になる方は参考にしてみてください。
小判はいくらで売れる?価値を決める3つの要素
.jpg)
小判の価値はすべて一律ではなく、主に以下の3つで決められます。
- 金の含有率
- 希少価値の高さ
- 小判の状態
高額査定を狙うためにも、どのような要素が価値を左右するのか理解しましょう。
金の含有率
価値を調べる際に重視されるのが、金の含有率です。
歴史的背景がある小判には、金が含まれています。金の量が多いほど貴金属としての価値が高まり、買取価格が上がる傾向があります。
しかし、すべての小判に同じ割合の金が含まれているわけではありません。金の含有率は発行時期によって異なり、とくに年代が古い小判ほど純度が高いといわれています。
たとえば、江戸時代初期に発行された慶長小判の金の含有率は86.8%です。一方、幕末の万延小判は56.8%と低く、貴金属としての価値は慶長小判ほど高くありません。
金の含有率は、信頼できる買取店で正しく鑑定してもらう必要があります。「小判だから絶対に価値が高い」と思わず、まずは査定に出して確かめましょう。
.JPG)
希少価値の高さ
希少価値の高さも、小判の買取価格を左右する要素の一つです。
基本的に、発行枚数が少ない小判ほど希少価値が高いと判断される傾向があります。発行枚数が少ない小判は市場での流通量も多くなく、コレクターからの人気も高いです。
たとえば、正徳小判は1714年5月~8月のわずか4カ月間 しか発行されなかったため、市場に出回る数が限られています。売却を考える際は、歴史的価値や発行枚数などの希少性にも目を向けると良いでしょう。
小判の状態
小判の状態も買取価格に影響を与える要素です。
たとえば、以下のような小判は買取価格が上がる可能性があります。
- 極印や刻印が鮮明に残っている
- 欠けがなく、隅々までしっかり形が残っている
- 細部のデザインまではっきりと残っている
- 汚れや変色がない
保存状態が良い小判は、美術品としての価値を求めるコレクターからの需要が高いため、価値があると判断されます。
査定額を下げないためにも、売りに出すまでは適切な環境で保管することが重要です。
小判はいくらで売れる?江戸時代の小判価値ランキング10選
.jpg)
ここからは、江戸時代に発行された小判の価値をランキング形式で10個紹介します。
小判ごとの特徴や歴史的背景、買取相場も紹介しているため、いくらで売れるか気になる方はぜひ参考にしてください。
価値ランキング1位|慶長小判
慶長小判は、江戸時代初期の1601年に日本で初めて発行された小判です。江戸幕府の初代将軍「徳川家康」の貨幣制度の元で鋳造されました。
金の含有率は86.8%と高く、買取相場も80万円~450万円と高値で取引されています。発行から数百年が経過しているため、保存状態が良ければ、査定額がより高額になる可能性があります。
表面には「ござ目」と呼ばれる細かい模様が施されており、独特の風合いがあるのも特徴です。知名度や市場での人気も高く、価値の高い小判として認知されています。
| 発行年度 | 慶長6年~元禄8年(1601年~1695年) |
| 金の品位(含有率) | 86.8% |
| 買取価格相場 | 80万円~450万円 |
価値ランキング2位|元禄小判
元禄小判は、江戸時代中期の1695年に発行された小判です。慶長小判の後に発行され、小判の流通量増加のために鋳造されました。
金の含有率は慶長小判より約30%少ない57.4%で、買取相場は130万円~350万円となっています。
裏面に「元」と極印が施されており、種類は長元・短元・偶然大吉の3つです。中でも偶然大吉や短元は、状態が良ければ高額買取が期待できるでしょう。
金の含有量は少ないものの、発行期間が1695年~1706年と短かったため、希少価値が高いと判断される場合があります。
| 発行年度 | 元禄8年~宝永7年(1695年~1706年) |
| 金の品位(含有率) | 57.4% |
| 買取価格相場 | 130万円~350万円 |
価値ランキング3位|正徳小判
正徳小判は、1714年に発行された小判です。発行年数が4カ月と短く、現存する数も限られているため、買取相場も100万円~300万円と高額です。金の含有率も84.3%と高く、慶長小判にも匹敵する価値があります。
正徳小判は、元禄小判や宝永小判の評価が悪かったことを受けて誕生した小判です。汚名返上のため、品位や量目を初代の慶長小判に近づけようと試みましたが、慶長小判のレベルには至らずわずか4カ月で姿を消すこととなりました。
市場ではほぼ出回らず、良い状態で見つかれば、さらに買取価格が上がる可能性があります。
| 発行年度 | 1714年 |
| 金の品位(含有率) | 84.3% |
| 買取価格相場 | 100万円~300万円 |
価値ランキング4位|安政小判
安政小判は、1859年6月~8月のわずか3カ月のみ鋳造された小判です。裏面に正の文字が極印されています。現存数が少ないため希少価値が高いとされ、買取相場は45万円~300万円ほどです。
当時、日本の貨幣制では銀貨を基準とした交換比率が採用されていました。しかし、日本と海外では金銀の交換比率に大きな差があり、この違いを利用して小判が大量に海外へ流出する事態が発生したのです。
こうした事態を受け、幕府は金の品位を維持しながら量目を半減させた安政小判を鋳造し、海外への流出を抑えようとしました。
| 発行年度 | 安政6年(1859年) |
| 金の品位(含有率) | 56.8% |
| 買取価格相場 | 45万円~300万円 |
価値ランキング5位|宝永小判
宝永小判は、江戸時代で3番目に作られた小判です。1695年に流通が始まった元禄小判の金品位の低下を立て直すために作られました。金の含有率は84.3%と高く、買取価格は10万円~280万円です。
金品位は慶長小判や正徳小判とほぼ同じですが、重さが比較的軽いため、貨幣としての価値はやや低く評価される場合があります。
しかし、大吉印が施されているものは希少価値が高く、保存状態が良ければ280万円と高額になる可能性があります。
宝永小判は、裏面に「乾」の極印が刻まれているのが特徴です。乾字小判とも呼ばれています。
| 発行年度 | 宝永7年~正徳4年(1710年~1714年) |
| 金の品位(含有率) | 84.3% |
| 買取価格相場 | 10万円~280万円 |
価値ランキング6位|享保小判
享保小判は、1714年~1736年に発行された小判です。正徳小判の金品位低下を受け、幕府が貨幣の信頼を回復する目的で鋳造しました。
現存数は多いものの、金の品位は86.8%と高いため、買取相場も30万円~130万円となっています。
慶長小判との違いは、表面に施されているござ目の間隔です。慶長小判は間隔が狭くて細かいのに対し、享保小判は間隔が広めに施されています。
正徳小判との見分けも難しいですが、表面下部の花押に刻まれている「光次」が判別のポイントです。正徳小判は「光」の6画目と「次」の4画目が重なっていますが、享保小判はそれらが離れています。
| 発行年度 | 正徳4年~元文元年(1714年~1736年) |
| 金の品位(含有率) | 86.8% |
| 買取価格相場 | 30万円~130万円 |
価値ランキング7位|元文小判
元文小判は、元文元年~文政元年にかけて流通した小判です。裏面には、真書体で書かれた「文」の字が入っています。約80年使われた小判のため、現存数も比較的多く、価値は10万円~180万円と幅広いです。
通常判の相場は10万円~15万円と低めですが、位の高い武士や大名に捧げる献上判は数百万円に及ぶ場合があります。
当時の江戸幕府は、貨幣不足によって武士や農民の財政難が深刻化していました。貨幣不足に陥った背景には、金や銀の供給が追い付かず、流通数が減少していたことが挙げられます。
元文小判は、そのときに経済状況を立て直すために作られた小判で、金品位よりも流通数の確保を優先して鋳造されました。
| 発行年度 | 元文元年~文政元年(1736年~1818年) |
| 金の品位(含有率) | 65.7% |
| 買取価格相場 | 10万円~180万円 |
価値ランキング8位|天保小判
天保小判は、裏面に「保」の文字が刻まれている小判です。1819年~1828年に流通していた文政小判の品位の低さを改善するために鋳造されました。
しかし、大きな改善は見られず金品位も低めのため、買取相場は10万円~180万円と保存状態によって変動します。
天保小判の種類は、通常版・偶然大吉・献上判の3つです。身分の高い武士や大名に献上する献上判の場合、数百万の査定額になる可能性があります。
また、日本で初めてローラーによる延金技術が採用された小判でもあります。他の小判と比べて表面が均一で滑らかなのが特徴です。
| 発行年度 | 天保8年~安政5年(1837年~1858年) |
| 金の品位(含有率) | 56.8% |
| 買取価格相場 | 10万円~180万円 |
価値ランキング9位|文政小判
文政小判は、元文小判の次に発行した小判です。価値は10万円~90万円と、江戸時代の小判の中でも比較的低めになっています。文政2年~文政11年に流通し、裏面には草書体で「文」の文字が刻まれているのが大きな特徴です。
文政小判は、元文小判の損傷をきっかけに作られました。元文小判は約80年使用されており、経年劣化で摩耗が進んでいたのです。そこで新しい貨幣が必要となり、誕生したのが文政小判です。
また、当時財政難に陥った幕府が少しでも利益を得るために作った小判だともいわれています。元文小判と比べて金品位が10%と低いため、そう長くは続かず1837年に天保小判へと切り替えられました。
| 発行年度 | 文政2年~文政11年(1819年~1828年) |
| 金の品位(含有率) | 56.4% |
| 買取価格相場 | 10万円~90万円 |
価値ランキング10位|万延小判
万延小判は、1860年に発行された江戸時代最後の小判です。幕末の財政難と海外への金流出を防ぐために鋳造されました。金の含有率が56.8%と低く、サイズも小さかったため、価値は7万円~60万円ほどとなっています。
明治7年(1874年)まで発行されており、比較的新しい年代の小判に当たるため、他と比べて価値が低いと判断されてしまうケースが多いです。献上判で状態が良ければ、60万円ほどになる可能性があります。
幕末を飾る小判として認知されており、雛小判や新小判とも呼ばれています。
| 発行年度 | 万延元年~明治7年(1860年~1874年) |
| 金の品位(含有率) | 56.8% |
| 買取価格相場 | 7万円~60万円 |
小判を高く売るための3つのポイント
.jpg)
小判をできるだけ高く売るには、事前準備が欠かせません。具体的に意識すべきポイントは、以下の3つです。
- 「触れない」「磨かない」「洗わない」を徹底する
- 付属品と合わせて鑑定に出す
- 信頼できる金買取店に鑑定を依頼する
利益を生み出せるよう、しっかり確認しておきましょう。
触れない・磨かない・洗わないを徹底する
小判を保存する際は「触れない」「磨かない」「洗わない」の3つを徹底しましょう。
高価買取が期待できる小判でも、状態が悪ければ価値が下がってしまう可能性があります。
小判は手の皮脂や汗が付着すると、表面の酸化や変色が進みやすくなります。落とすと変形して価値が下がる可能性もあるため、手が触れないように注意しましょう。
また、研磨をすると、古い小判が持つ独特の風合いや時代を感じさせる趣が損なわれてしまいます。表面に傷が付いたり、極印が削れたりする可能性があるため、磨かないようにしましょう。
とくに墨書きが施されている小判は、ブラシなどで磨くと文字が薄れてしまいます。
小判をキレイに魅せようと洗浄するのも避けた方が良いでしょう。洗浄すると傷が付くだけでなく、洗浄液の成分で変色する可能性があります。
少しでも保存状態の良い状態で売るためにも、余計な手を加えないようにしましょう。
付属品と合わせて鑑定に出す
小判を売る際は、付属品も一緒に査定に出すことで買取価格が上がる可能性があります。付属品が付いている小判は、コレクター市場で高額取引されている傾向があるためです。
たとえば、発行元の証明書や鑑定書があれば信頼性が増し、買取価格が上がりやすくなります。小判の価値を正しく鑑定してもらうためにも、忘れないようにしましょう。
また、箱から発行された年代を推測できる可能性があります。小判の希少価値の高さを証明できる要素にもなるため、箱があれば合わせて鑑定に出してみましょう。
信頼できる金買取店に鑑定を依頼する
小判の鑑定は、信頼できる金買取店に依頼しましょう。
小判は、価値が高いものほど真贋の見極めが難しくなります。そのため、経験豊富な鑑定士がいる買取店でなければ、小判本体の価値を正しく判断できない可能性があるのです。
信頼できる金買取店を見極めるには、複数社に鑑定を依頼して査定額が適正か比較するのがポイントです。査定額だけでなく、ホームページなどで買取実績やサービスの質も確認しましょう。
当社「ゴールドウィン」では、経験豊富な鑑定士が小判の価値を正確に査定いたします。お客さまに高い利益を還元できるよう、金相場の変動に基づいた高価買取価格を実現いたします。小判の買取査定はゴールドウィンにお任せください。
まとめ|小判がいくらで売れるか知りたいなら鑑定に出そう
小判の買取価格は、保存状態や発行枚数、鋳造年数、市場での需要などによって異なります。中でも、金を多く含むものや慶長小判のような江戸時代初期に作られた小判は、高額で取引されやすい傾向があります。
価値が高い小判ほど真贋の判断が難しくなるため、売る際は信頼できる金買取店に依頼しましょう。
小判の買取を検討している方は、ぜひゴールドウィンへご相談ください。当社では、単に重さだけで価値を判断するのではなく、金相場や小判の刻印、保存状態、歴史的価値まで細かく査定いたします。
他店で付けられた価格をご提示いただければ、それに上乗せした買取価格を提案できるよう努めます。
店頭買取はもちろん、宅配買取や出張買取も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
小判がいくらで売れるかに関するよくある質問
純金小判50gの買取価格はいくらですか?
純金小判50gの買取価格は、金の市場価格や買取手数料、小判の状態によって異なります。基本的には、金の含有率が高いほど価値が上がる傾向があります。買取店のホームページに金の相場が記載されている場合があるため、一度確認してみると良いでしょう。
小判の価値を現在に換算するといくらになりますか?
小判1両が現在の貨幣価値でいくらになるか正確に算出するのは難しいですが、日本銀行金融研究所貨幣博物館では、お米の価格を基準に目安を示しています。
総務省の調査によると、現在の東京都のお米5kgの小売価格は4,363円です。この価格を基に、江戸時代の米1石(約150kg)=1両として換算すると約13万円になります。概算すると、小判1両の価値は現在の15万円前後に当たると考えられます。
参考:総務省|小売物価統計調査(動向編)主要品目の東京都区部小売価格
参考:日本銀行金融研究所貨幣博物館|江戸時代の1両は今のいくら? ―昔のお金の現在価値―
ゴールドウィン 梅田店 店長 中村監修 古物許可番号621010160159